民 草 の 闘 い ―日本電気硝子公害と万福寺― |
| 渡部 瞭(会員) |
|
はじめに
鵠沼きっての古刹、鵠沼山(こうしょうざん)万福寺の裏門を出てすぐ西側の石垣の上に、下のような記念碑がひっそりと建っている。碑文は万福寺の荒木良正住職(鵠沼を語る会会員)の手によるものだが、極めて簡明で読みやすい。
その冒頭に、田中正造の歌が掲げられている。いうまでもなく、足尾銅山による渡良瀬川の鉱毒事件で被害者住民とともに闘った国会議員で、数々のエピソードが今日まで伝えられている。この事件は今から百年余り前に起き、別子銅山鉱毒事件とともに、日本における公害問題の原点とされる。「公害」の語が一般的に定着するのは、水俣事件が明るみに出た1960年頃のことだが、この語自体は明治時代から使われていたらしい。公的に用いられた例としては、東京都が1949(昭和24)年に「公害防止条例」を作ったのが最初とされる。
 この碑が建てられて間もなく、《藤沢市鵠沼神明公害対策委員会》は、公害闘争の経緯を『ここに歴史あり ―公害闘争と住民運動―』と題する175ページの報告書にまとめて刊行した。これは市内の図書館・文書館などで閲覧できるので、詳細はそちらに譲るとして、ここではその概要と背景を解説してみたい。
藤沢南部の工業化
現藤沢市南部の明治以後の近代工業は、鉄道開通によって本格化する。初期はいわゆる農村立地型工業で、農業生産物を加工する製糸業(生糸紡績)や澱粉・アルコール醸造という分野が中心だった。この時代にも、工場の廃液が引地川に流され、魚の大量死が報告されたり、騒音や悪臭に周辺住民が被害を受けたりしたこともあったが、いずれも小規模・短期間のものであった。
金属加工分野では1921(大正10)年進出の東京螺子(らし)(現ミネベア)を嚆矢とし、関東大震災の復興期あたりから昭和10年前後の時代、小松製作所(小松熟練工業→関東特殊製鋼)さらには日本精工・高井精器といった工場が伸びてくる。これらは軍需工場として、大戦中に発展した。戦後は沈滞するが、朝鮮特需が復興のきっかけとなった。
1956(昭和31)年の経済白書は、「もはや『戦後』ではない。われわれは異なった事態に直面しようとしている。回復を通じての成長は終わった。今後の成長は近代化によって支えられる」の有名な一節があることで知られる。
それから5年、「60年安保」の政治の季節を経て、池田内閣は「所得倍増」を旗印に経済の季節へと国民の目を向けさせるのに成功した。高度経済成長時代の到来である。東京オリンピックを契機に高速自動車道路や新幹線が整備され、陸上における物流の主流は鉄道から自動車へ転換した。県内でも、東京湾岸には自然海岸が消え、大型埋立地に「重厚長大型」を中心とする臨海工業地帯が発展していった。1961(昭和36)年に制定された農業基本法は、都市近郊の農業離れに拍車をかける結果をもたらした。相模湾側では、それまでの農業用地を潰して、電機・電子・精密機器・自動車関連・化学・薬品・食品等々の極めてヴァラエティーに富んだ各種工場が立地するようになった。
藤沢市南部でも、主に東海道線沿線に工場進出が目立った。これは、鉄道騒音の関係で住宅地に向かず、農地として残っていた安価な土地を自治体が斡旋したものである。そうした工場の多くは、通過する列車の乗客への宣伝効果を狙って、外装や看板・電飾、植栽・造園に工夫を凝らした。地理学者=田中啓爾は、これらを「車窓工場」と名付けている。
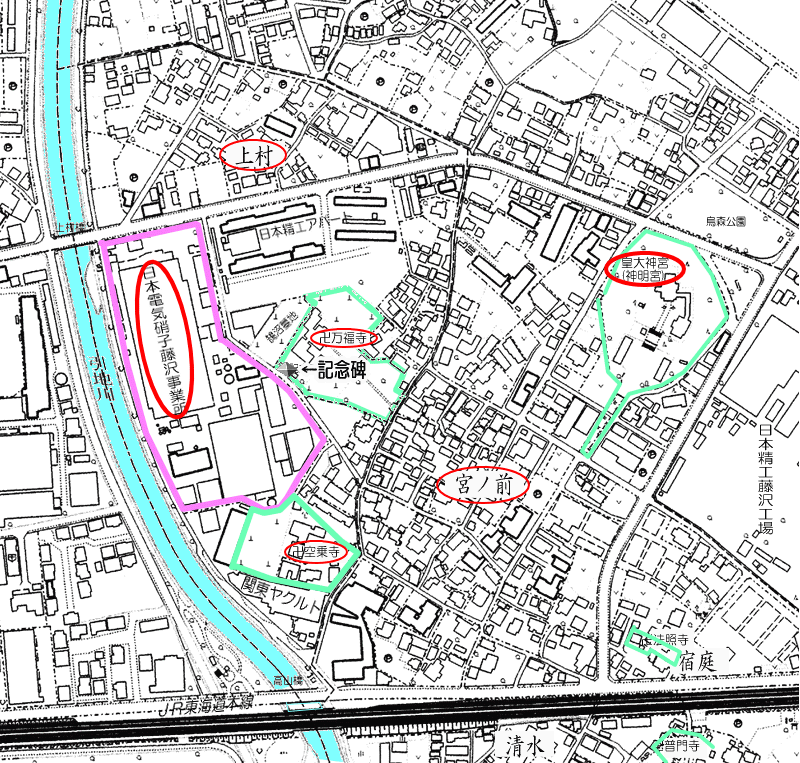 鵠沼地区では、1958(昭和33)年に関東ヤクルト製造、その翌年に日本電気硝子(ガラス)が鵠沼神明3丁目の引地川に面したところに隣り合って相次いで進出した。鵠沼地区におけるある程度の敷地規模を持つ工場進出の最後の例である。すなわち、日本電気硝子は鵠沼で最も新しい工場らしい工場ということになる。
この2工場が建った場所は、万福寺・空乗寺(くうじょうじ)という古刹の裏手にあたり、引地川改修以前の地形図では測量のたび毎に曲流の様子が変化する不安定な地形上に位置する。そのために利用価値が低く、開発の手から取り残されていた。
「元祖鵠沼」宮ノ前と上村
日本電気硝子のすぐ東側には宮ノ前、北側には上村(かむら)という集落が隣接する。この両集落は、いわば「元祖鵠沼」ともいうべき伝統を持つ、極めて古い集落なのである。平安末期の大庭御厨(おおばのみくりや)が鎌倉権五郎(ごんごろう)によって拓かれた中心地だったろうし、奈良期にあったという高座郡(たかくらごおり)土甘郷(とかみごう)50戸というのも、このあたりを指すと考えられる。さらに遡れば、一帯は西宮越遺跡と総称される遺物包含地で、弥生式土器や古墳時代の土師器(はじき)・須恵器も発掘されている。この宮越・宮ノ前という地名からも解るように、神社を中心に発達してきた集落といえよう。その神社こそ土甘郷総鎮守に位置づけられる神明宮(皇大(こうだい)神宮)であり、その基礎となったのは延喜式内社の石楯尾(いわだてお)神社とされる。少なくとも千年以上、あるいは2千年も前から、人間生活が、おそらく絶えることなく続けられてきたという土地柄なのだ。
有賀密夫氏の調査によれば、鵠沼本村を代表する9集落のうち、明治初期における戸数は、宮ノ前が45戸で最大、上村は11戸で最小の集落であった。
封建社会における農業集落においては、村落共同体という地縁的社会結合が見られたことはよく知られるところだが、鵠沼のような砂地で生産性の低い土地しかない上に、藤沢宿の助郷(すけごう)と鉄炮場(てっぽうば)の役負担という労働分担を強いられていた集落においては、村落共同体の役割はより重要であったと考えられる。また、庚申講や地神講などを含むさまざまな宗教行事、冠婚葬祭などが、村落の人々の結束を強めていった。
先にも見たように、鵠沼地区においては高度経済成長期に農村としての性格は急速に失われ、専業農家は現在は1軒しか見られない。農家といってもほとんどがいわゆる第二種兼業農家に過ぎない。しかし、「本村」においては、かつての村落共同体の名残をみつけることは、さほど困難ではない。古くからの年中行事や稲荷講などはまだまだ残っているし、皇大神宮の祭礼における幟立てや人形山車、祭囃子の継承などは、集落の結束を強める好機となっている。
日本電気硝子とは
さてここで、鵠沼に進出してきた日本電気硝子㈱とはどのような企業なのかを、同社のホームページを参考に探ってみたい。
日本電気硝子は、戦時下の1944(昭和19)年10月、日本電気㈱(現、新日本電気=NEC)などの出資により、滋賀県大津市で設立され、電球や真空管のガラス部分を製造していた。戦後、日本電気㈱大津製造所にてガラス事業を再開し、1949(昭和24) 年12月1日、同社より分離独立、この頃は真空管用ガラスや管ガラスを手吹きで生産していた。1951年1月、ダンナーマシンによるガラス管の自動成形に成功、1956年にタンク炉による連続生産に移行し、管ガラスによって事業基盤を築いた。
そして、1959(昭和34)年に藤沢工場(現、藤沢事業場)を開設し、1965年、ブラウン管用ガラス(白黒)事業に進出、1968年にカラーブラウン管用ガラスの生産を開始した。以来、日本のテレビおよびブラウン管産業の発展とともに成長してきた。一方、超耐熱結晶化ガラスや建築用ガラスブロック、電子部品用ガラス、ガラスファイバなどの生産を開始し、ブラウン管用ガラスを主力とする世界有数の総合特殊ガラスメーカーに発展した。
騒音・煤煙・粉塵=第1期日本電気硝子公害問題
碑文を読んでみると、この公害闘争には2つの時期があったことがわかる。
第1期は、日本電気硝子が鵠沼に工場を建てて間もなく、周辺の人々が工場の発する騒音や震動に迷惑を感じたことが話題になり、農作物や樹木が枯死するに及んで、これも工場が建ってからの現象だと気付いたことから始まる。
1963(昭和38)年11月、上村・烏森・宮之前の3町内会は連名で神奈川県と藤沢市に対し、日本電気硝子藤沢工場から出る騒音・煤煙・粉塵による被害について、善処方の陳情を行った。公害闘争のスタートである。
県・市は日本電気硝子に対し陳情内容を指摘、会社側は煤煙・粉塵の調査は県・市に依頼し、独自で騒音調査を行った。その結果は基準値を若干超える箇所を数か所認め、年末に出された県の指導書に対してはコンクリートブロックを積み重ねてその対策とする程度に止まり、住民の満足が得られるものではなかった。住民側は次年度の7月に市に対して騒音・排ガスについて再度陳情した。
一方、会社側が県・市に依頼していた煤煙・粉塵の調査結果は、万福寺・空乗寺の樹木における亜硫酸ガス接触害を顕著とし、含有量は市の調査では一般数値としたが、県(農業試験場で分析)は極めて顕著と認めた。そしてその原因は亜硫酸ガス排出量の多いC重油を用いている工場排煙にあるとし、C重油を使用する近隣2工場のうち、卓越風向から見て日本電気硝子藤沢工場がその原因であると結論付けた。この結論に基づく県の改善指導に対し、当初会社側のとった態度は極めて消極的かつ緩慢なものであった。これに業を煮やした住民側は、工場に隣接する日本精工アパートの関係者、農業協同組合なども参加して組織の規模を拡大し、粘り強く会社や自治体と交渉を持った。最大の被害者でもある万福寺の荒木住職夫妻(夫人は上村出身)は、終始指導的立場にあり、会合などに寺の施設を提供した。万福寺はこの公害闘争の拠点となっていったのである。
1955年の神通川イタイイタイ病(富山県)、1956年の水俣病公式発見(熊本県)、1962年の四日市喘息(三重県)、1964年の阿賀野川第二水俣病(新潟県)のいわゆる四大公害病をはじめ、全国各地で公害闘争が持ち上がり、メディアの話題にもしばしば採り上げられたため、国民の関心も高まっていった。
こうして住民の粘り強い交渉、マスコミの世論喚起などに押されて自治体も指導を強化した。碑文にもあるように、この段階では藤沢市の態度は消極的で、むしろ神奈川県の姿勢の方が強かった。これは、この問題を担当した部署が、市の場合は市内商工業の推進を担当する商工課だったのに対し、県は公害課が担当したせいであろう。市は当該工場を積極的に誘致した事情もあった。
1966(昭和41)年に入っても会社側の腰は重かったが、4月1日に開かれた県・市・町内会・日精アパート関係者・寺院と会社側の取締役・工場長による第6回対策委員会で、ようやく具体的な取り組み姿勢を見せた。これを受け、4月10日に念書を提出した。その主な内容要旨は次のようなものである。
①有害ガスの除去対策は煙突の嵩上げと集合煙突化を年度内に行う。
②粉塵除去は従来のサイクロンに加えてパックスフィルターを早急に設置する。
③騒音対策はコンプレッサー室・ボイラー室外側に防音壁を早急に設置する。
④公害の補償は、具体的に今後充分話し合いの場を持ち、解決に努力する。
この念書を受けて、被害者側は4月15日に町内会で検討、翌日会社側に次のような要旨の要望書を手交した。
①煙突の集合化は、年度内といわず、夏までに完成させること。
②震動防止対策が抜けているので、騒音対策に併せて早急に措置すること。
工場側は早速工事に取りかかり、この間、被害者側はその成果を検証すべく、各種の測定・調査を重ねた。煙突の集合化は結局12月までかかり、年度内が年内にまで、若干短縮された。
かくして、1963(昭和38)年11月以来の粘り強い闘争は、一応の決着を見た。しかし、問題はこれで解決したのか、被害者住民側は完全に納得したわけではなかったし、煙突の嵩上げは、有毒ガスを希釈する効果はあったとしても、被害範囲を拡大する恐れもあった。
全国の動きを見ると、1967(昭和42)年に公害対策基本法が制定され、翌年には大気汚染防止法と騒音規制法が、さらに1970年に水質汚濁防止法が相次いで制定されて、1971年には環境庁が設置されている。このことは、高度経済成長のツケが公害問題という形で拡大し、その対策が国家規模で取り組まれていった過程を物語る。
鉛中毒=第2期日本電気硝子公害問題
1971(昭和46)年3月、被害者住民側の危惧は、恐るべき形で具体化した。
同月9日の市議会で、中西国夫市議(共産)が質問に立ち、「日本電気硝子藤沢工場で従業員の中に鉛中毒患者が出ており、周辺に鉛公害を撒き散らしている疑いが強い」と指摘し、市側の対応を質したのである。当該患者7人は、氷川下セツルメント病院(文京区)の山田医師の診断で異常に高い汚染レヴェルを示したと報道された。会社側は「環境基準は守っている」と答えている。
神奈川県労働基準局は翌10日、藤沢労基署に会社側の代表を呼び、立ち入り検査の結果欠陥が発見された鉛中毒防止装置の改善を求める命令書を手交した。
この問題に対する周辺住民の対応は素早かった。前期の公害闘争で組織されていた《上村公害除去対策委員会》を補強し、《鵠沼神明公害対策委員会》を結成、12日には住民大会を開催したのである。住民大会では24か条の会則を採択し、宮崎誠一会長以下23名の役員を選出、顧問相談役に関根久男市議(故人・宿庭在住・日本精工労組出身・鵠沼を語る会会員)を据えて、本格的な闘争態勢を整えた。また、会社側に説明を求め、その煮え切らない態度に住民側が憤然となる場面もあったという。さらに、①会社の移転、②問題解決までの操業停止、③計画表の提出を求める要望書を手交する一方、16日には鉛中毒症の学習会を開いた。
これに対する会社側の回答は、18日に①移転・操業停止には応じられない、②住民に対する集団検診を行いたい、③計画表については《覚書》の形で提出された。これを受けて、翌19日に第2回住民大会が開かれた。その中で①会社側の検診を拒否、②公害資料の収集と学習、③資金カンパ、④自治体側への出席の要請、⑤自費検診の領収書保管などが話し合われた。その模様は同席したNHKや5大新聞(朝日・毎日・読売・サンケイ・東京)により3月下旬から4月上旬にかけて大きく取り上げられ、この公害闘争は全国的に知られるところとなる。
3月20日、当該工場従業員の鉛中毒患者が重症で入院したにもかかわらず、26日の住民総決起集会に招かれた会社側は鉛公害の事実を強く否定し、住民側との溝は深まった。4月にはいると工場周辺の土壌からも高濃度の鉛が検出され、これに不安感を深めた周辺住民は、万福寺に氷川下セツルメント病院で公害病に取り組んできた山田信夫医師を招き、自主検診の機会を持った。その結果、強い自覚症状を持つ住民13名のうち12名までが鉛中毒と認定された。
藤沢市も第一中学を会場に、労働災害の権威とされる横浜市大医学部の山賀岑朗教授による講演会を開催し、県とともに山賀教授を中心とする医療チームを組織して、5月末には住民の集団検診に踏み切った。会社側が提案した検診を住民がボイコットしたためである。その結果は、4人に1人は異常は認めながらも鉛中毒と認定される患者が出なかった。一方、山田医師による6月20日の第2回自主検診では、新たに94人を鉛中毒と認定、市側の集団検診によるゼロと大きな食い違いを見せた。この差はどこから生まれたのだろうか。自主検診では高度な技術を要し、厳密な結果が出る《誘発法》を用いたのに対し、市側の集団検診では、一般的な《採血法》を用いたためと、ある新聞は分析している。この結果は、住民側に市に対する不信感を募らせたし、住民決起集会に呼び出された会社側は、市の発表を楯に鉛公害を認めなかった。
この間、5月前半には、公明党の調査で新たにフッ素公害の疑いも見つかり、市は県に対し日本電気硝子藤沢工場の全面操業停止などの強い措置をとるよう公文書で依頼した。県は同工場の一部操業停止命令を発するに至る。さらに、藤沢市議会は6月15日、住民から出された工場移転の請願を、全会一致で採択した。夏を迎える頃、闘争はデモ行進・座り込みなど厚みを重ねるとともに、《市政を明るくする市民の会》で、「もはや全市的問題だ」と論議され、湘南教祖が「子どもの命と健康を守る」立場から教研集会で問題提起し、日本電気硝子本社工場のある大津市の市民団体から連帯の申し出があるなどの広がりを見せる。
秋に入ってついに会社側は鉛公害を認め、操業再開を断念するなど、態度の変化を見せる。何年かぶりに美しく色づいた木々の葉を見て、人々は公害の恐ろしさを改めて認識した。と、ここまでを紹介して『ここに歴史あり』の記述は、いきなり1982(昭和57)年の闘争終結まで話が飛ぶ。
この間に何があったのかを、冒頭に紹介した記念碑から読み取ろう。「一方、新藤沢市長葉山峻は、深くこの問題を愁い、吏員を督励し早期解決を図らしめ、斡旋に務めた。かくて、炉の移転・規模の縮小・酸化鉛の不使用となり、又、鉛中毒患者の治療も進んだ。遂に昭和五十七年三月、被害を受けた社寺・町内会に補償金を支払い、公害問題の局を結んだ。」
葉山市長は、出馬前、夏の座り込みにも参加し、住民側に連帯感が生まれていた。この公害闘争は、荒木住職・宮崎会長・関根市議といった優れた指導者に恵まれていたが、何よりも村落共同体に培われた民衆の粘り強い底力の勝利といえよう。記念碑の冒頭に掲げられた田中正造の歌の語を借りれば、民草の力が虐げの力を跳ね返した闘いであった。それに終始深く関わった2人の鵠沼を語る会のメンバーがおられた。本来この稿は、彼らによって書かれるべきものである。
この闘争から会社側も多くのことを学んだ。現在の日本電気硝子㈱藤沢事業所は、《ISO14001》《ISO9000》をいち早く取得し、環境問題・省エネルギー問題に積極的に取り組む模範的事業所に位置づけられている。
|
| (わたなべ りょう) |