|
���J��H�� ���a110���N�A�v��40���N�L�O���W
���J��H�`�k��l
�@
�@�n ���@��(���)
�@
|
||||
|
�͂��߂��@�@�����䂩��̉�Ƃ͑������A���Ȃ��Ƃ��吳���ȑO�̉�Ƃł́A���̂قƂ�ǂ��ݕʑ��Ȃǂ̑؍ݎ҂ł���A�����ɍ������낵����͋H�ł���B
�@���J��H�́A�������\���闷�ق������s�����t�̓��ڏ���=�����̈�l���q�ł���A�t�����X���w����A�����Ă����10�N�Ԃ͓����̐��ׂɋ����\���A��ƂƂ��Ă̊����̃X�^�[�g������B�܂��A�ƒ됶������������n�܂����B����ɁA�e�މ��ҁA�F�l�m�l�A��a�w�����m�̋����q�ȂǁA�䂩��̐l�X�����ł����Ȃ��炸�����ɂ��Z�܂��ł���B
�@���ĕM�҂́A��w�����x86���Ɋ��u����ŏo������O�l�̍����l�̎d���@�\�V��F���Y�E���J��H�E�����琤�\�v�̒��ŘH���Љ���B����ȑO�́w�����x�ɂ��H�̖��͎U�����邪�A����������فs�����t�Ɋւ���L�q�̒��Ŗ��O���Љ����x�ł���A�l������Ɛт��Љ��@��͂Ȃ������B
�@2003(����15)�N�A�H�̂��⑰���瓡��s�ɍ�i22�_�̊�����A������������̍����s���Z���^�[�V�فA�������y�����W�����ŏ��i�W���J���ꂽ�B
�@���N�t�ɂ͎s���M�������[�Ŋ��ꂽ�S��i����I����A����ɍ��킹�č������y�����W�����ł́u�����������E�I��ƁE�ʐ^�Ǝ����ɂ�钷�J��H�W�v���J�Â����B�M�҂�100���ɋy�Ԃ��̓W���Ɍg���@��A���J��H�Ƃ����l���̑��ʐ��Ɩ��͓I�Ȑl���ɂ�������S��D���A�܂��A�W���鑽���̕��X�Ɛڂ��A�@�������̎��ɓ������������`���������Ǝv���Ɏ������B
�@
���������@�@���J��H��(�{��=���O)�͍����炿�傤��110�N�O��1897(����30)�N�V���X���ɓ����Ő��܂ꂽ(���J��H�̏Љ�ɂ́A�_�ސ쌧���܂�A�����o�g�A�����̓����͘H�̐��ƂȂǁA���܂��܂ɏ�����Ă�����̂��U������邪�A����������)�B
�@���O�[�㒘�w�����E�������ٕ���x�ɂ��A��=�������g(1855-1916)�͓����̎łŎ��g�ݕ��������Ă����l�ŁA��=����(1866-1938)�͋���ˎm�Ƃ������钷�J��d��̖��ł������B
�@�����ō����Ƃ̂������̐[���A�����̎���=���J��Ƃɂ��ĐG��Ă������B�����̗��e�̒��J��d��E����v�Ȃ́A��������ɂ͓����E�����ɏZ��ł����B�v�Ȃɂ͒j�P�l�A���U�l�A�v�V�l�̎q�����������A�����͚�܂����B�햅�̖ʓ|����������㒷���̖������ʂ�������=�����́A�ɂ߂Ă���������̂ł������Ƃ������X�̃G�s�\�[�h���c���Ă���Ƃ����B�_�y��\�y���̖�����=�s�g�F�t�̏����������Ă����O��=����A����(�����ʂ�)�C�݂Ɉɓ����s���݂������فs����(���Â܂�)�t�̏��㏗��(������)�ɃX�J�E�g�����̂́A�H���Ɛ������O���a���������̂��Ƃł������B
�@�w��ɒB�������O�́A�~�b�V�����X�N�[��=�s�Ő����{�Z�t�ɓ��w���A��h�ɂɓ���B��ɘH�̓G�b�Z�C�w�����x�̒��ŁA�u���̏f�ꂪ�o�c���Ă����u���Â܂�v�Ƃ������ق��A�����̉Ƃ̂悤�ɂ��ď��N������߂������B�v�Ə����Ă���B�c���̍�����A���܍�����K���@��������̂��낤�B
�@���O�����w�Z�R�N���̂Ƃ����e�͗������A���O�͕�=������������邱�ƂɂȂ������߁A���J�쐩�𖼏��A���J�열�O�ƂȂ����B����Ƒ��O�サ�Ē��J��Ƃ͓��������������A�����Ƌ��ɓ����̎��ӂɈڂ�Z�͗l�ŁA�{�Ђ��������Ɉڂ���Ă���B
�@��̎��ɐ��܂ꂽ�̂����J��ƗB��̒j���ł��钄�j=�ɑ��ł���B�ɑ��Ƃ��̍�=�^�P�Ƃ̊ԂɁA��l���q�̋Ԉꂪ���܂ꂽ���A���O�Ƃ͎O�Ⴂ�̋Ԉ�́A�c�����ɕ������E���A������̑O��ɒ��J��Ƃ������Ă���B�Ԉ�͒����ɉƓ𑊑����A�㌩�l�ɂ͈ɓ����s���A�������A�����҂Ɠ`�����Ă���c��=��������݂ŁA���J��Ƃ��������ċԈ����Ă邱�ƂɂȂ����B
�@���̍��A�ɓ����s�����ق�����ʌ�����o�g�̈�t=���c�Ǖ����@���Ɂs�����C�_�a�@�t�������ɗאڂ��ĊJ�݂����B��ɕ��c�Ǖ��͒��J��Ƃ̎l��=���ƌ��������B��l�̊Ԃɂ͎q�����܂�Ȃ������̂ŁA�Â̌����{�q�ɂ���B���O�ƋԈ�A����̓�l�̂��Ƃ��A���Ɍ���̎o������܂߂ē����͊i�D�̗V�я�ł������B�N���̗��O�́A�ނ�̖ʓ|���悭�����̂ŕ���Ă����B
�@���̉��ɂ́A���̂Ǝ��X�Ƃ�����l�̖����������B���X�͌㓡�@�h�Ƃ�����ɒ��J��Ԉ�̌㌩�l�ƂȂ�l���ƌ�������B �@�@�@ �@
���w�����@�@1910(����43)�N�A���O�͋Ő����{�Z�ɐi�w�����B��h�ɐ����͓��R������ꂽ���A�A�Ȃ����Ƃ��ȂǁA�����̑؍q�Ƃ��𗬂����܂ꂽ�B�u�J��搶�������Ԃ��Â܂�̗�����~�ɑ؍݂��ď����������Ă����B���ς�����̎��́A�悭�̂����ɂ����Ă��َq�������B�v�Ƃ��u�ݓc�����搶�����Ă����邱��A�ʐ��ɏo�����鎞�A���Ă����Ď���ꂽ���Ƃ��������B����ł�����Ɏd���Ԃ�����Ă����B�A��ɂ͊G�̋����������ē��X�Ƃ������̂ł���B�v�Ȃǂ̎v���o���L���Ă���B�i�w���M�T���P�C�x���a39�N3�����j
�@���O�͖�������̒��w���Ƃ��Ă͂��Ȃ�i���I�ōs���I�ł������B�Ⴆ����Ȏv���o���L����Ă���B�u���炭�A���{�ōŏ��ɃO���C�_�[���������Ă̂����̂��A���Ƃ��̖l�ł�����A�����݂����Ȃ��b�ł���܂��B����A�܂������M�����Ȃ��悤�Ȃ��b�ł���܂��B�ǂȂ����}���قɍs���āA�����l�\�ܔN�̎����̍����V�����A���C�悭�T���Č䗗�Ȃ����B���̖l�����Ă���ʐ^����ŁA�f�J�f�J�ƌf�ڂ���Ă���̂���������ł���B�v(�������q��w�w�����ڂ́x�V��1965.3)
�@�܂��A�T�N���̏H�ɂ͋��F�Ɩ��ω���ɗ��s�B���ɖ����A��h�����肷��B
�@�������A1914(�吳3)�N�̉Ăɒ��J�열�O���N�͕a��̐×{�̖ړI�Ŗk�C���́s�g���s�X�g�C���@�t�ɂЂƉĂ��߂������B
�@�u���h���Ă������l�A�O�ؘI������Ɛe�����Ȃ����̂͂��̂���ł���܂��B�v�ƘH�͋L���Ă���B�u�܂��O�ؘI������͌|�p�̑����ɂ��Đ�����Ă��܂����B�v�Ƃ���(�w�����V���x���a38�N12��15��)�B����Ɂu���J��N�͉�ƂɂȂ肽�܂��B�|�p�ƂɂȂ��Ă������������̂���l���������̂��v�ƌ����A�u�����ĐM�������Ƃ��ˁB�t���A���[���R�̂悤�ȑf���炵���@�����`�����܂��B�������ɂ̂���悤�Ȍ�����C���@�̋���ɕ`���āA���Q��ɂ���l�тƂ�����������ȁB�l���͒��I�̂��Ƃ��|�p������H�s�łł��邱�Ƃ�m��˂Ȃ�Ȃ��v�Ɨ@���ꂽ(�w�o�g�o�x���a41�N10����)�B
�@���́A�O�ؘI�����v�l�Ƌ��ɐ�����ăN���X�`�����ɂȂ����̂́A�H�̎����x���A1922(�吳11)�N4��16���A�����Ղ̓��ł������B
�@�Ƃ�����A���̎O�ؘI���Ƃ̏o��́A���̌�̒��J�열�O�̐��U�ɑ傫�ȉe����^�������Ƃ͊m���̂悤���B
�@�k�C������߂��āA���̔N�̕��A���J��H�͋Ő��̃n���x���N���[�h�_����������A�N���X�`�����ɂȂ���(��w�����x86���ɕА�����łƂ����̂͌��)�B���疼��Lucas(���J�B�����̖�ł͘H��(���J)�������J�͈�t�Ɖ�Ƃ̎�쐹�l)�B�u�H�v�̉덆�͂���ɗR�����邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�@��ɗ��O�͎O�ؘI���Ɂw���h�~�j�R���x�Ƒ肷�鐅�n����������đ������B���̎��͂��炭�O�؉Ƃ̏��̊Ԃɏ����Ă����悤�ŁA������̉ĂɍȂ̕ꂪ��̉Ԃ����|���ɑ}�����̂����āA�u���̉ԂɃ_������Y�����������h�~�j�R�̊G�̕��ɂ�������v�Ƃ̈�r�܂�Ă���B
�@���݂��̎��͘I���̈⑰�ɂ��O��s�Ɋ���A�s�O��s�R�{�L�O�L�O�فt�Ō��J���ꂽ�B���炭�����ŌÂ̒��J��H�̏@���G��ł���B
�@���āA�N������������吳�֑ւ��ƁA���{��d�ɑ傫�ȓ]�@���K�ꂽ�B
�@1898(����31�j�N�A�������p�{�Z��Q��Z�����������q�V�S���r�˂���Ď��E�����ۂɁA����I�ɓV�S�Ƌ��Ɏ��E�������p�Ƃ����́s���{���p�@�t�����������B���̓W����s���{���p�@�W����(�@�W)�t�ł���B���{���p�@�͓V�S��r�˂������A�s���h�t�s�y���h�t�ȂǓ`���I�ȉƌ����x���d�����鋌�h�́s���{���p����t�ƑΗ��\�������m�����Ă����B����₷��ړI���當���Ȃ��e�h������`�ō��Ǝ哱�̑�K�͂Ȍ���W�A���Ȃ킿���W�Ƃ���1907(����40�j�N�ɊJ�n�����̂��s�����Ȕ��p�W����(���W�j�t�ł���i������s�������W�t�Ƃ��Ăԁj�B������{���p�@�́A1910(����43�j�N�A���q���{�X�g�����p�ْ����E���{���p�����Ƃ��ēn�Ă������Ƃɂ��A������̉��U��ԂƂȂ�A���{���p�@�̃����o�[�����W�ɏo�i����悤�ɂȂ�B
�@1914(�吳�R)�N�A���W�̐R�������O���ꂽ���R��ς�́A�O�N�ɉ��q���v�������Ƃ��_�@�ɂ��̈�u�������p�������������A���{���p�@���ċ�����B�����Ă��̔N��10���A�ċ���P��s���{���p�@�W����(�@�W)�t���J����A���̋L�O���ׂ��W����ɒ��w�T�N���̒��J�열�O�͏o�i���A�����I����̂ł���B�o�i��͍����C�݂ŋ��Ԃ��������t�̎p��`�����w�l�ӂɂāx�Ƒ肷�鐅�ʉ�ł�����(�T�n)�B���N�̍ċ���Q��@�W�ɂ��w�H��̗��x[����]�����I���Ă���B
|
||||
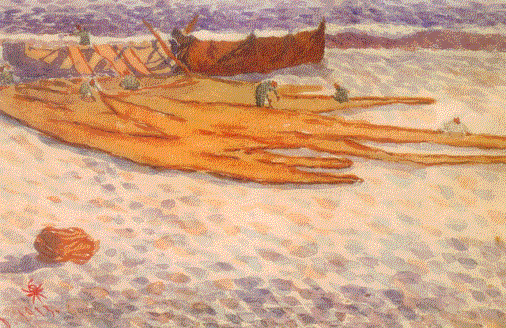 �@ �@ |
||||
| �w�l�ӂɂāx[����]�F1913�@�ċ���P��s�@�W�t���I�� | ||||
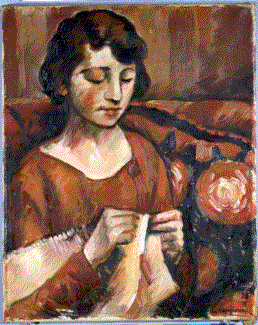 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
|
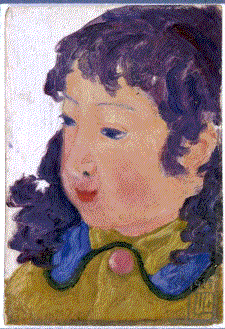 |
|||
| �w���q���j���x[����]�F1925(�ʐ^��:���k���Y��) | �w�������x[����]�F1915�@(�ʐ^�F�ΎR�Ɓj | |||
| �@���̒i�K�ŗ��O���ǂ̂悤�Ȏ�i�Ŕ��p���w��ł������A���邢�͒N�Ɏt�����Ă����̂��͎c�O�Ȃ���ڂ炩�ł͂Ȃ��B���ɏЉ�����n��A���ʉ�̑��ɖ��ʉ������Ă���B�w�������x�Ƒ肳�ꂽ��i(�T�n)�́A�]���̕��c�����`�������̂ŁA1915�N�Ƃ��邩��A���w���ƌ�A���邢�́A�����̕������猩�āA���ƒ��O�̓~�̍삩������Ȃ��B�eLUC'�Ɣ��ǂł���T�C����������B���̗��N�ɂ��łɐ��疼��Lucas���덆�ɍl���Ă����Ƃ���Β��ڂɒl���悤�B
�@�Ő����{�𑲋Ƃ������O�́A�������p�{�Z(�����Y�p��w�̑O�g)���������A�P��ł̓p�X���Ȃ������B�����덡���̂����\�{�̔{�����ւ�S���œ�ւ̎ł���B�������i�͊�Ղɋ߂��B�ă`�������W�ō��i�������O�͓V����Ƃ����ׂ��ł��낤�B
�@���̂P�N�ԂɁA���J��Ƃł͑傫�Ȏ������������B
�@1916(�吳�T)�N�P���A�f��̓����̏��㏗��=���J�� ������@��̊��q�̕a�@�Ŏ��������̂ł���B
�@���̂��Ƃɂ��A���O�̕�=�������������p�����ƂƂȂ����B�ːF�����̂�̎�Łu���m�h�v�Ƃ��Ă̖������Ă��������́A��������҂̂����̎�ɂ��Ó쐏��̖����قɔ��W���Ă����B
�@���́A�吳���O���́A�킪�����̕ʑ������n�s�����C�ݕʑ��n�t���قڊ����i�K���}���A�ؑ�������̑�ʑ��ɉ����āA���K�͂ȑݕʑ����������݂��ꂽ�B�����ݕʑ��̏Z���ɂ͎Ⴂ���m(�s�����h�t�̕��ҏ��H���āA�����c�Ȃǁj����(�s���y�Ёt�̊ݓc�����A�� ��Y�A���x�p���Y�Ȃ�)������A�ނ��K�₷��|�p�Ƃ�o�Ől�A�W���[�i���X�g�Ȃǂ������ɏh��������A�𗬂̏�ɗ��p���邱�Ƃ������A�����͌|�p�Ƃ̃T�����Ƃ������ς��������Ƃ����B
�@���Z�ɐi�H���A�A�Ȃ����܂Ȃǂɂ����������͋C�ɐG���@������������ł��낤�B
�@���̂���A�����ɂقNj߂���(�͂���)�Ƃ̕ʑ��ɁA���O���Q�ΔN��̗m���=�� �ɔV��(1895-1977)���؍݂���悤�ɂȂ����B�ɔV����17�ɂ��ās�q���E�U����t(���t���E�U����)��P��W(1912�N)�ɖ���A�˂��Ƃ������n�ȉ�Ƃł���B�N����Z�����߂���l�́A�����Ό𗬂��������悤�ł���(�w�����x83���Q��)�B
�@
���Z�����@�@1916(�吳�T)�N�̂S���A���O�͓������p�{�Z���{�`�Ȃɐ���ē��w���A�G�i���J(����������)�ɏZ�ނ��ƂɂȂ����B
�@���Z�ŘH�́A�����f�u(�������イ)(1881-1938)�Ɏt�������B
�@�f�u�́A1881(����14)�N���݂̕��Ɍ��_��S���蒬�ɐ��܂ꂽ�B�{���͋P�v�B���w�ҏ��� ���̎q�ŁA��t�̏��� �C�A��Ȉ�ʼn̐l�̈��ʑ�(�݂��₷)�A�����w�҂̖��c���j�A�C�R�R�l�Ō���w�҂̏����×Y�̒�A���ɂ����u�����܌Z��v�̂T�Ԗڂł���B
�@�f�u�́A���h�̋��{��M(���ق�)(1835-1908)�Ɋw���A��a�G�̌������u���ďZ�g�h�̎R���ы`(��悵)(1836-1902)�̖剺�ɓ������B1899(����32)�N�������p�{�Z���{�`�Ȃɓ��w�B1904(����37)�N�A���Z����Ȃő��Ƃ���B���Z���ƌ����a�G�ɌX�|�A���̐^������i�ɐ��������Ƃɒ����A�F���A�\�}�̏�ɓT��ȏ����������B1908�N����1935�N�Ɏ���܂œ��Z�ŋ��ڂ��Ƃ�A������{��d���\�����Ƃ����X�Ɛ��ɑ���o�����B��\�I�Ȓ�q�Ƃ��ẮA���N���ɗ�L����A�������(��������)�A���R����(���傤�ǂ�)�A���ؕ۔V���A�R���H�t�A���V�^��A��c�����A���R�ѐ�(����)�A�g�����v�A�����u��(������)�A�R�{�u�l(���イ����)�A���R �J(�₷��)�A���{�����A���R�C�Y�炪����B
�@���Z�P�N�̉āA�H�͋��F�ƒ��N���璆�����k���𗷍s�A���̈�ۂ��w���N���i�ΎR�x[���ʁA��k�ЂŏĎ�]�Ƃ��Đ��삵�A�H�̍ċ���R��s�@�W�t�ɏo�i���A�������I���ʂ������B
�@�H�̔��Z���w�O�ɋN��������ꎟ���E���́A���[���b�p�̎�v�s�s���œy�Ɖ����A���E��̎哱���͕č��Ɉڂ�X�����������B���{��`�̐��n�͔��p�E�ɂ��傫�ȉe����^���A�`���I�Ȍ|�p�̒Nj�����A���Ɣ��p�⌚�z�A�����ȂǁA����O�I�Ȕ��p�ւƐV�����W�J�������鎞����}�����̂ł���B
�@���{�̔��p�E�ł́A1919(�吳�W)�N�ɂ́s�隠���p�@�t�̔����ɂƂ��Ȃ��āA�s�������W�t�́s�隠���p�@�W�����i��W�j�t�Ɖ��̂���B
�@���̑�Q���W(1920�N)�ɘH�́w�G���j�����Y�S�M�x[���{��]���o�i���A���I�����B�J�g���b�N���{���=���J��H�̃f�r���[��Ƃ����Ă悩�낤�B
�@���J��H�̃f�b�T���͂́A�l��{�D��A�f�u�ȊO�̋���������������ڂ���Ă����炵���B���̂��Ƃ́A��ɑؕ����̘H�����[�������p�قŃh���N�����́w�^���W�[���̕����x��͎ʂ����Ă����Ƃ���ɔ��Z�����̌���f��(�䂤���@���߂�)���ʂ肩����A�H�ɐ���lj�̖͎ʂ�Őf���A���傤�Ǘ��������ꑾ�Y���������Љ��(��q)�Ƃ����G�s�\�[�h������M���m�邱�Ƃ��ł���B
�@���J��H�͏����f�u���獑��̎�@����������Ɗw�ю��A���̌��ʂ𑲋Ɛ���Ɍ����������B���Ɛ���͑���w������鋳�k�x�Ƃ���119.8×180.0cm�̎��{���F(���قႭ���傭)�A���q��(������)�̍�i�ŁA���݂������Y�p��w��w���p�قɏ�������Ă���A�����p�ق̃z�[���y�[�W(http://db.am.geidai.ac.jp/object.cgi?id=2581)�Ō��邱�Ƃ��ł���B
�@����H�́A�w������Ɂs�����B���Z���V�I��t�Ƃ����J�g���b�N�̌b�܂�Ȃ��l�X�ւ̕�d�c�̂ɏ������A���������炵���B
�ؕ������@�@1921(�吳10)�N�A�������p�{�Z�𑲋Ƃ����H�́A�T���ɂ͓��{�X�D�s���Ίہt�̎O���D�q�Ƃ��ĒP�g�t�����X�������B
�@�ދ��ȑD����H�̓f�b�L�ɏo�ăX�P�b�`�����邱�Ƃŕ��炵�Ă����ɈႢ�Ȃ�������`�����ޓ����D�q�������B��������Ƃ̓���=����`�e(�悵����)���(1886-1976)�ł���B��݂̒m�l�̂��b�ɂ��A�����̓����݂́A���̎��A�W���z�[��(�}���[�����암)�̔ˉ�(�X���^��)�ɏ�����Č�(��ϵ)���Ɍ������Ƃ��낾�����B��݂͎Ⴂ��Ƃ̍˔\��F�߁A������\���o�Ă��ꂽ�B��݂Ƃ̓V���K�|�[���ŕʂꂽ���A��l�̊W�͐��U�������ƂɂȂ�B
�@���N�̏t�A�����Y�p��w��w���p�قŁs�p���ց@�m��Ƃ����S�N�̖��t�Ƒ肷�铌���Y�p��w�n��120���N�L�O�W���J����A�Ăɂ����Ă͐V�������ߑ���p�قł��J�Â��ꂽ�B�H����������1920�N��́A����120�N�̗���̒��ł��ł����m�ρX�ȓ��{�l��Ƃ��n����������Ƃ�����B��ꎟ���œr�ꂽ�s�x��=�G�|�b�N�t�̌���Nj�����|�p�̕����Ɓs�A�[��=�f�R�t���@�ɖu�����鏤�Ɣ��p�̐V�W�J�̎���ƈʒu�Â�����p�j�Ƃ�����B��ƂɂƂ��ċɂ߂Ďh���ɕx�ގ�����}���Ă����B
�@�H�̏ꍇ�A�����������m���p�̓`�����w�сA�V�X���ɐG��A�J�g���b�N���p�̓`���I�ȋZ�@��g�ɂ��悤�Ƃ������R�̑��ɁA���p�w�Z����^����ꂽ���������������Ƃ��i�M(�����̂�)�S����(�O�����������p�فA����B�������p�يw�|��)�͎w�E���Ă�����B�u���������y�p�g�����؍ݒ����m�É�m�������Ϗ��v�Ƃ������߂��Ă����Ƃ����̂ł���B
�@�P�����]��̑D�����I���A���Ίۂ̓}���Z�C���`�ɒ���~�낵���B��������͋D�ԂŃp���Ɍ������B
�@�H�͍ŏ��ɍ��c���P�ȗ����{�l�ɂ䂩��̐[��Charles(�V������) GUERIN(�Q����) (1875-1939)�Ɏt���A���ʂ𒆐S�Ƃ���m��Z�@���C�������B���m�G��̎嗬�͖��ʂ�����ł��낤�B�߂��߂��Ƙr���グ���H�́A���N�́sIndependent(�A���f�p���_��)�t�ɏo�i���A���X�N�ɂ́sSalon(�T����) d'Automne(�h�[�g���k)�t�ɓ��I�A��i�wUne Famille�x[����]�̓��[�����p�ٔ����グ��i�ɑI���B
�@�H���n�����ĂQ������A�� �ɔV�����p���ɓ����A���w�������n�߂�B��l�̃p���ł̌�F�W�ɂ��Ă͖��m�ȋL�^��������Ȃ����A�p���̓��{�l��w���w���͕p�ɂɌ𗬂��Ă����͗l�Ȃ̂ŁA���Ȃ��F�W�͔Z���������Ƒz���ł���(�w�����x83���Q��)�B�܂��A1922�N�̃A���f�p���_���ł́A�H�ƈɔV���̍�i������œW������Ă����Ɠǂݎ���L�^������B
�@�����1922�N�A�O��w�Z���C�����]��̒��J��Ԉ���A�H�̌��ǂ��悤�ɉ��Ίۂœn�������B�D�͓��������D���͈ꓙ�������B����͒��J��Ƃ̌ˎ�ł���Ԉ���d�����邽���̔z���������Ƃ�����B
�@�Ԉ�͉��y�]�_�Ƃ��Ă���A�s�\���{���k��w�t�ւ̓��w��ڎw���Ă����B�����ł̎���Ɠ��l�A�H�ƋԈ�̋����������n�܂�A�Ԉ�͑�w�̏����ƌ�w���C�ɂ������B
�@�Ƃ��낪1923�N�X���P���̊֓���k�Ђœ����͑S��B�I�[�i�[�̗��ꂾ�����Ԉ�́A���������̂��߁A�u���ŋ}篓��{�Ăі߂����B
�@����A�H�̓t�����X�Ɏc�藯�w�����𑱂��邪�A����͒P�ɊG��Z�p�K���݂̂Ȃ炸�A����ɂ킽����̂������B
�@
�{���T�}���^���@�@�w���J��H�敶�W�x�̔N���ɂ͑吳10�N�̋L�q�Ɂu�˒˕����̊��߂ɂ��{���T�}���^���ɉ�����ă����h���ɍs���v�Ƃ���B
�@�sBon Samaritan�t�Ƃ́A�V���ɂ���u�P���T�}���A�l�v�̃t�����X��ǂ݂ł��낤���Ƃ͔��f�ł��邪�A����ȏ�̂��Ƃ͔���Ȃ��B���ꂱ��Y��ł����Ƃ���A������������ �����w�l�Ԃ̕��ہ\�_���≺�s��x�Ƃ������������݂������������B����ɂ��ƁA�����������Ƃ炵���B
�@1920�N�H�A�����h���x�O�̃`�F���V�[�ɐQ������̐����𑗂郔�@�C�I���b�g=�X�X�}���Ƃ������C������K�˂��≺�s��́A�ޏ��̐M�����̐[���ɐG��Ċ��������B�����Ŋ≺�́A�������[���b�p�Ŋw��ł����Ő��̌�y�A�˒˕����A���q�M���Y�A���J��H�������h���ɌĂъāA�S�l�ŃJ�g���b�N�̐N�`���c��g�D���邱�Ƃ�ژ_�B���ꂪ�s�{���T�}���^���t�ł���B����͂���ȏ�ɂ͔��W���Ȃ��������A���ꂼ��鋳�̈ӎu���ł߂��悤�ł���B
�@���ł��ł��Ⴂ�H�́A�C��������J�g���b�N���p�̓������߂��A���ǂ��̓��ɐi�ނ��ƂɂȂ����B���q�M���Y�͏����������A�E���o�m��w(���@�`�J���ɗׂ荇���鋳�t�{���̂��߂̋��c������w)�Ɋw�Ԃ��ƂɂȂ邪�A���r�ފw�����ē��{�ɋA������B���ǁA�≺�s��A�˒˕����̂Q�����_���Ƃ��ē��{�J�g���b�N�j�ɖ����₷���ƂɂȂ�̂ł���B
�@�≺�s��(���킵����������)(1889-1940)�͐M�B����˂̎m���o�g�̎��Ɖ�(�O�䕨�Y���o�ēd�́A�a�сA�����A��s�Ȃǂ̌o�c�Ɍg���)=�≺����(���悿��)�̒��j�B�Ő��ŘH�̐�y�ɓ�����B�Ő����{�Z�Q�N�̎��Ɏ��A�J�g���b�N�̐M�k�ƂȂ�B���̎��̋����͐�y�̎R�{�O�Y�ŁA��ɑs��̖�=��q�ƌ������A�s��̋`��ƂȂ�B�Ȃ��R�{�O�Y�́A�J�g���b�N�А�����䂩��̎R�{�����Y�̎O�j�ŎR�{�M���Y�̒�ł���B
�@�s��͋Ő����ƌ�ꍂ������N�{�ȂŘa�ғN�Y�A��S������Ɠ����B�P�[�x���Ɏ��i���A�M���V����A���e����Ƃ��������[���b�p�ÓT���w�ԁB��呲�ƌ�A����(������)�̋��d�ɗ��������A1919(�吳�W)�N�A������b���ɂ�莄��ʼnp���ɗ��w�B�����h���̃Z���g=�G�h�����Y��_�w�Z�Ő_�w���C�߂���A���F�l�c�B�A����̐��E�ɂ�苳�c�����E���o�m��w�Ɋw��Ŏi���ƂȂ�A���F�l�c�B�A���悩��h�����ꂽ�鋳�t�Ƃ��ċA������B
�@�A����̔ނ́A���������_�ɃJ�g���b�N�w���̎w��������T��A�m���l�_���Ƃ��Č��M��U�邤�B�����i����Ɉڂ����ނ̌㔼���́A1931(���a�U)�N�ɏA�����x�m�R�[�̃n���Z���a�{�݁s�����a�@�t�̉@���Ƃ����d���ɕ�����ꂽ�B
�@�˒˕���(�Ƃ��@�ӂ݂���)(1892-1939)�͊C�R�R�㑍��=�˒˕��C�̎q�B�Ő��ŘH�̐�y�ɓ�����B�ꍂ�������{���ɐi�ށB�ꍂ����Ɏ��A�J�g���b�N�̐M�k�ƂȂ�B���̎��̋������߂��̂��≺�s��ł������B
�@1921(�吳10)�N�A�H�Ɠ����N�Ɉ�w���w���Ƃ��ēn�����A�X�g���X�u�[���̃��C=�p�X�g�D�[����w�Ɋw�сA�A����͈�t���i�����_���Ƃ��āA���j�ɋꂵ�ސl�тƂ̂��߂ɕa�@��Ȃǂ̊����������B�A�����������B
�@
�lj�͎��@�@20���I�����A���[���b�p�e���̒T�����������Đ���𒆐S�Ƃ���A�W�A�e�n�ň�Ղ@���A�����̈╨�����[���b�p�Ɏ����A�����B���ɂ͕lj����������͂�����Ď����������������B
�@����ɐS�����߂������隠��{�̏��{�����Y(�܂����낤)�����A���s�隠��{�̑ꑾ�Y��������́A���߂Ă����͎ʂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤���Ɩ͍����Ă����B
�@�͎ʂɂ͊m���ȋZ�p���������l�����K�v�ł���B�����Ŕ��H�̖�𗧂Ă�ꂽ�̂��t�����X���w���̒��J��H�������B
�@���{�����ƘH�Ƃ̐ړ_�́A1924�N�u���b�Z���ŊJ���ꂽ���ۊw�p��c�œn�������ہA��g�ق���˗�����ĘH���ʖ�߂����Ƃɂ��A���{����M�����ꂽ�ƌ���Ă���B���{����̖͎ʈ˗������߂͌Ŏ��������A����̕lj悱�����{���p�̌����Ƃ����w�E���H�����f�������B
�@�H��ꑾ�Y�������Ɉ������킹���͓̂������p�{�Z�̌���f�������ł���B���̌o�܂͐�q�����B�́A�H�̖͎ʊ��Ԓ��A��Ƃɕt���Y���Č����̑��̃}�l�[�W�����g���������B
�@�ݕ����{��g�قɏo���肵�Ă��� Serge(�Z���W��) Elisseeff(�G���Z�[�G�t) (���V�A�v���O�ɃT���N�g�y�e���u���O�ɂ������G���Z�[�G�t����̌䑂�i�ŁA���V�A�ǂ݂̖��̓Z���Q�C�B�x��������w�ɗ��w���A�V�� �o(����ނ炢�Â�)�ɏo������̂��@�ɓ��{���w���u���B�����隠��{�����Ȃ�45�N�ɗD�G�Ȑ��тő��Ɓi�O���l�Ƃ��ď��̑��Ɛ��j�A�Ėڟ��̖剺�ł��������B���V�A�v����t�����X�ɖS���A�A���B���̍��̓p����w���������@����������)�𒇉�҂Ƃ��Č����i�߂�ꂽ�B
�@�悸�̓p���̃��[�������p�فA�M�������قɎ�������Ă��� Paul(�|�[��) Pelliot(�y���I)�@ (1878-1945�@�^�����~�n�𒆐S�ɃV���N���[�h����T�������t�����X�l�̌���w�ҁB������Ȃǐ�������ɑΉ����邱�Ƃł��������j�̃R���N�V�����A�H�͂����̂���40�_�߂���͎ʂ��邱�Ƃ��ł����B
�@�����ăx�������̃t�F���P���N���f�����ق���уC���h���p�قɔ[�߂��Ă��� Albert(�A���x���g) von(�t�H��) Le Coq(���R�b�N) (1860-1930�@�����A�W�A�ōl�Êw�I���@�������h�C�c�l�̒T���ƁB�����w�����A�W�A��@�L�x�͒������ɂɂ��Ȃ��Ă���j�̃R���N�V�����̑�����H�͖͎ʂ��邱�Ƃ��ł����B�������A����̍ۘA�����R�ɂ��x�������U���Ō����̑���������ꂽ���߁A�H�̖͎ʂ����c���Ă��Ȃ����̂��قƂ�ǂŁA�l�Êw�I�A���p�j�I�ɋM�d�ȍ��Y�Ƃ�����B
�@����ɑ�p�����ق��������Ă��� Aurel(�I�[����) Stein(�X�^�C��) �� (1862-1943�@�����A�W�A�̊w�p�����ɑ傢�ɍv�������n���K���[�n�p���l�̍l�Êw�ҁA�T���ƁB�����A�W�A�ł̓^�����~�n�𒆐S��1906-1908�N�A1913-1916�N�A1930�N�ƁA�R��̉������s�����ق��A1910�N�ȍ~�C���h�̍l�Êw�������肪���A1912�N�Ƀi�C�g�݂ɏ����ꂽ�j�̃R���N�V�����A�H�͂��̂���30�_�ȏ��͎ʂ��Ă���B
�@������H�͑������R�N�̍Ό��������ďW���I�ɖ͎ʂ����B
�@��ʂ̉�Ƃ����K�p�ɖ͎ʂ���̂ƈႢ�A�l�Êw�I�Ȏ����Ƃ��Ė͎ʂ���̂ł��邩��A�u�d�˕`���v�Ƃ����Ē��ɍ�i�ɘa�����d�ˁA�Ƃ��ɂ߂����Ċm���߂Ȃ���ʂ����Ƃ������@�Ő��m�ɖ͎ʂ��s��ꂽ�B
�@�H�̖͎ʍ�i�͌��ݓ������������فA������w�A���s��w�A�����Y�p��w�Ɏ�������Ă���B���̐��͘H�̋L�^�ɂ���125�_�ɋy�ԁB
�@���̊Ԃ̎�����p�M�S�����̌����w�������������ٕۊǒ���������͎ʂƒ��J��H�x(�������������ٌ������wMUSEUM�x��572��)�ɏڂ����B
�@�������������ق̓��m�قR�K�W�����ł́A���̘H�̖͎ʂ����݂�����I�Ɍ������Ȃ���W�����Ă���B
�@���̕lj�͎ʂƂ����o���́A���{�̃t���X�R�lj�̃p�C�I�j�A�Ƃ��āA���̌�̒��J��H�̃��C�t���[�N�ɂ��傫���𗧂����ɈႢ�Ȃ��B
���ی��@�@��Ɂu��g�ق���˗�����ĘH���ʖ�߂��v�Ə������悤�ɁA�ݕ����{��g�قł́A�p���ɑ؍݂��Ă�����{�l���w����ʖ�Ƃ��Čق����Ƃ������������炵���B
�@�������H�̏ꍇ�A�ʖ�ɉ����ē��{��ƂƂ��Ă̓��Z���������ꂽ�B
�@1921�N�ې��{(��̏��a�V�c)�K���̕ԗ�Ƃ��āA�����p���ɍݏZ���Ă��������{���F��(�₷�Ђ�����)(1887-1981)�v�Ȃ́A�x���M�[������K��̍ہA�u���b�Z���̓��{��g�قŔӎ`����Â����B���̎����J��H�A�O�Y ��(���܂�)(1884-1946)�����Ȃ��A�O�Y �̓A���A���̂��A�H�͐ȉ�(���ȂŊG��`���������I�Z�@)���I�����B�}���[=�A�����G�b�g���܂���u���̉Ԃ��v�ƒ��������H�́A�����܂����[���̓��̉Ԃɔ�ы��鉍��Y���ĕ`���グ���B
�@���̐l�I�́A���炭�p���̓��{��g�ق��s�������̂Ǝv����B�O�Y �͉���������������ʓ��{���\����I�y���E�̃v���}�h���i�ł��������A�H�̕��͔��Z���o�ĊԂ��Ȃ���y�҂ł���B����(���܂�)�����p���ݏZ�̓��{�l��Ƃ̒��ł��V�Q�҂ɉ߂��Ȃ��������낤�B���̘H�ɁA���s�����獑�J���̂̑����S�킹���̂́A��قǂ̕q�r�Ƃ����G�ꍞ�݂��������ɈႢ�Ȃ��B�H���g�A�u�Ђ⊾���̂̎v���o�v�ƋL���Ă��邪�A�傰���ɂ����Α���{�鍑���p�E�̑�\�I��ƌ����܂ꂽ�킯�ł���B
�@1925�N�s�x���������{���p�W�t���J���ꂽ�B��\�Ƃ��ď������_(��������)(1874-1945�@�{���原�Y�B���d�̏d��)���n�ƁB�H�͂��̓W����ɍ�i���o�i���Ă������ǂ����s�������A�x�������̃t�F���P���N���f�����قŐ���lj�̖͎ʂ����Ă������߂ɁA�J��ɌĂꂽ�炵���B�J��Ƀq���f���u���N�哝��(1847-1934)���ՐȂ����B���{��ƂƂ��ďЉ��A����������H�͔��Ɋ��������ƋL���Ă���B�H��27�̎��ł���B
�@�Ȃ��A�s�x���������{���p�W�t��1930(���a�T)�N�Ăɂ��J�Â���Ă���A������̕����K�͂��傫���A�悭�m���Ă���B
�@��ꎟ���E���I���ɔ���1926�N�s�p�����ۍq��ψ���c(�H�͖����q���c�ƋL�q)�t���������{��g�قŊJ�Â��ꂽ�Ƃ��A�t�����X��\�Ƃ��ăt�H�b�V������(1851-1929)���o�Ȃ���(���{��\�͓c����(���Ȃ�����)���k(��������)���m)�B�ŏI���̃p�[�e�B�[�ɐȉ���I���邽�߂ɏ����ꂽ�H�́A�����̂��߂ɉ_�C�ɏ��鈮���ƕx�m��`���Č��サ���B
�@�H�͗��w���ɑ�ꎟ���̗��Y�ɐڂ���@����킯�ł���B
�@
�t���X�R�E���U�C�N�@�@1926(�吳15)�N�A���w�������㔼�ɓ���A�H�͋��_���p����x�̃t�H���e�[�k�u���E�Ɉڂ��A�s�t�H���e�[�k�u���E�������t�ɂ�Paul(�|�[��) Albert(�A���x�[��) BOWDOIN(�{�E�h����)(1844-1931)�Ƀt���X�R��A���U�C�N��Z�@���w�ԁB
�@�{���C�^���A��� fresco �Ƃ́q�V�N�ȁA�ł����Ắr���Ӗ�����`�e���i�p��� fresh �ɂ�����j�ŁA�����Ƃ��āA����(��������)��h���Ă܂��Ȃ����ꂪ�܂�������Ȃ������ɕ`����@�A����т��̂悤�ɂ��ĕ`���ꂽ�G��Ɍ��肵�ėp�����A���ʁA�t���X�R�Ƃ͂��̈Ӗ��Ŏg����B
�@���z���̑����@�Ƃ��āA�Ñ�A�����A���l�T���X�̒����ɂ킽�胂�U�C�N�ƕ���ŏd�v�ŁA���U�C�N�ȏ�ɕ��y�������t���X�R�́A�������ɖ��ʉ�ɁA�����ă^�u���[��ɒn�ʂ�����A18���I���Ō�ɂقƂ�ǐ��ނ���B�������A20���I�ɂȂ��āA�ǖʂɒ��ڂɑ�������K�ȉ�@�Ƃ��čĂуt���X�R�ւ̊S�����܂�Astrappo(�X�g���b�|)(�ɁB�p��� strip )�Ƃ����A�P(�ɂ���)�Ȃǂ�p�����͂����Z�@�̊J���ɂ��A�����̍�i���C���A���삳���悤�ɂȂ����B
�@���̋Z�@����{�l�Ƃ��ď��߂Ė{�i�I�Ɋw�сA�e�n�ɏ��Ȃ���ʍ�i���₵�A�܂������̌�p�҂��琬�������l�҂����J��H�ł���B
�@���U�C�N��Ƃ͑嗝�A���ЁA�F�K���X�A���̑��̍d���ȑf�ނ��G�̋���L�����o�X�ɒu���悤�ȃC���[�W�Ŕz�u���A�����܂Ȃ��~�����ׂāA�lj�⏰������|�p�̋Z�@�łł���B�t���X�R�������L���X�g�����p�̓`���I�ȋZ�@�ł���Ȃ�A���U�C�N�͌Ñ㓌���L���X�g��(�r�U���e�B��)���p�ő��p���ꂽ�Z�@�Ƃ����悤�B���ꂪ�����ɂ͐��m���p��C�X�������p�ɂ��e����^�����B
�@���{�ł́A����������P���I�Ƀ��U�C�N�|�p��������悤�ɂȂ邪�A�U�������悤�ɂȂ����̂͐��̓����I�����s�b�N���J���ꂽ���납��ŁA�H����Ă��sF.M�lj�W�c�t(��q)�̉ʂ����������͑傫���Ƃ�����B
�@
�A�[��=�f�R�@�@1925�N�S�`�T���A�sExposition Internationale des Arts(�A�[��) Deco(�f�R)-ratifs et Industriels modernes(����Y�Ƒ����|�p���۔�����)�t���p���ŊJ�Â��ꂽ�B���ɂ����s�A�[��=�f�R�t�ł���B���́s���{���p�فt���݂ɂ́A�p���ݏZ�̓��{�l��Ƃ��������ċ��͂����B�ܘ_�A�H�����̈�l�ł���B
�@�����̃p���ɗ��w���Ă������p�Ƃ̎傾������G��͎��̒ʂ�ł���B
�@���R���O(1883)�@���@���O�Y(1883) �����V�F(�䂫�Ђ�)(1884)�@�c�� ��(1886)�@�y�c���A(1887)�@���c�d���Y(1887)�@�~�����O�Y(1888)�@��i���Ӊ�(1889) ����|��[��](1889)
���J ��(1891) �����P���Y(1892) ���R ��(������)(1893) ��[�\�V��(1893) �R�`�Y(1894) �Ɍ��F�O�Y(1894) �؉��F��(1894) ��������(1895) �� �ɔV��(1895) �с@�`�q(������) �O�c����(1896) ���R�h�O(1897) ���J��H��(1897) �����S�O(1898)�@�� ���V��(1898)�@�C�V����V��(1904)�@��(�@)���͐��N
�@�����Ĕނ�̏�ɌN�Ղ��Ă����̂��A����20���I��������G�R�[���E�h�E�p���̕��_�����������c�k��(���͂�)(�����I�i�[��=�t�W�^)(1886-1968)�ł���B
 �@���1923�N�S���Q���A�~�����O�Y�𒆐S�ɍݕ����{�l��ƒ��ԂŎB�����ʐ^�B������H�A������Q�Ԗڂ����c�A�H�̑O���~���ł���B���̎ʐ^�͋A������m�l�ɑ����ĕ�=�����̂��Ƃɓ͂���ꂽ�B���ʂɂ͕M�����Łu���l �ݔb�� ���O ���������Ԗڂ̕����c�k�����Ɍ䐢�b�ɂȂ��ċ��܂��v�Ƃ���B �@���1923�N�S���Q���A�~�����O�Y�𒆐S�ɍݕ����{�l��ƒ��ԂŎB�����ʐ^�B������H�A������Q�Ԗڂ����c�A�H�̑O���~���ł���B���̎ʐ^�͋A������m�l�ɑ����ĕ�=�����̂��Ƃɓ͂���ꂽ�B���ʂɂ͕M�����Łu���l �ݔb�� ���O ���������Ԗڂ̕����c�k�����Ɍ䐢�b�ɂȂ��ċ��܂��v�Ƃ���B
�@�s�A�[��=�f�R�t�̊J���ꂽ1925�N�A�x���M�[�̃u���b�Z���ł��s �u���b�Z���������p������t���J�Â���A�H�͂��̓��{���p�ٌ��݂ƒ�ɎQ�^���A�q���I�|���h�V���o���G�M�́r����͂��Ă���B
�@���̎��`���ꂽ�w���q���j���x(�T�n)�͓����x���M�[�ɕ��C���Ă����O�H�����̈��P�g�v�l�����f���B��㖭�q���͏��D�����P�q���̒��o�ŁA�w�����P�q�̎l�o���x�ɏЉ��Ă���B���v�Ȃ͌�ɍ����������ɋ����\���A���q�v�l�́s���J��H�W�t�J�Ò���2004�N�U��16���A�����ő��E���ꂽ�B���N101�B
���w�㔼�@�@�H�̑ؕ���1921�N����1927�N�̂U�N�Ԃقǂ����A����܂ŐG��Ȃ���������̏o�������L���Ă������B
�@ 1925(�吳14)�N�ɂ̓��@�`�J��=�V�X�e�B�i���p�قɁwIntroduccion del Cristianismo en Japon�x[���{��]�������B���̍�i�͌��݂ł������p�ق̃z�[���y�[�W(http://mv.vatican.va/4_ES/pages/x-Schede/METs/METs_Sala05_01_01_031.html)�Ō��邱�Ƃ��ł���B
�@��1926�N�A�sSalon d'Automne�t�ɁwUne femme de Cagnes�x[����]���o�i���A���I����Ƌ��ɁqSilver(�V�����@�[) Star(�X�^�[)�r�܂���܂��ăT�����̉���ɐ������ꂽ�B
�@�܂��A���̔N�A�sEcole du Louvre(�G�R�[���@�h�D�@���[����)�t�̐��m�����j��Ȃ��C�������B���̎����͋A����̘H�ɕ��������w�@�����߁A����̏��q��w�Ȃǂŕ����j���u����Ƃ����d����ۏ��邱�ƂɂȂ�B
�@1927�N���X�A�sSalon de Paris�t�ɁwNue�x[����] ���o�i���ē��I���ʂ������̂��Ō�ɁA���J��H�̓t�����X�𗣂��B
�@
���������@�@1927(���a�Q)�N���t�A�N�����吳���珺�a�ɑւ���ĊԂ��Ȃ����{�ɘH�͋A������B
�@�Ȃ����̓����́A�����ƋԈ�̎�Ō��Ⴆ��悤�ɕ�������Ă����B�n�C�J���D�݂̋Ԉ�̈ӌ��ɂ����̂��A�r�����߂Ė{�i�I�ȃe�j�X�R�[�g���Q�ʐݒu����Ă������A�{�ق͍X�Ɋg������A�_���X�z�[���܂Ő݂����Ă����B�������ďÓ쐏��̃��]�[�g���قƂ��āA�����\����n�ʂĂ����̂ł���B
�@�Ԉ�͋A������H�̂��߂ɁA�����ׂ̗���n���ȃA�g���G��p�ӂ��Ă���Ă����B���ꂪ�ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������́A���c�N��������ʍe�Ő��I�ȗ��ꂩ�������Ă�����̂ŁA������ɏ��肽���B
�@�����ł͊C�O���w�o���҂͂��ꂱ���|���Ď̂Ă�قǂ��邪�A���a�����̓��{�ł́A�܂��܂����l���������B
�@�����ɏ��a�Q�N�S���R���̉��_�f�ՐV��́u�`���c�}���v�Ƒ肷��L��������̂ň��p���悤�B
���V��(�ӂ����͂܂�)����(�ق�)��Ƃ��鐢�E�I(�������Ă�)���`��(��������͂�)���J��(�͂�����)�H��(�납��)�̟c�}��(��������킢)�͋��q����(���˂����Ⴄ���Ⴄ)�ȉ����Z�L�u(������)��ᢋN(�ق���)�̉�(����)�Ɉ��(����)�ߌ�(����)�Z��(��)��荔���C��(�����ʂ܂�������)����(���Â܂�)�ɉ�(����)�ĊJ��(��������)���ꂽ��o(����Ђ�)�c(�����)���(��)���H��(�납��)���F��(������)�ꖇ(�܂�)��(�ÁT)��(����)��ꂽ
�@�Ȃɂ���u�����ւ�Ƃ��鐢�E�I��攌�v�Ƃ��ċA�������̂ł���B
�@�H���ؕ�����1921(�吳10)�N�A���t= �����f�u�́A���R�����A��c�����A������A�������O��Ɓs�V����a�G��t���������Ă����B
�@�A����������̘H�́A��V��s�V����a�G��W�t�Ɂw�A�����u�}���E���[���b�p(�M���V���_�b)�x[�ڽ�]�A�w�{�x[���{��]�A�w�فx[���{��]���o�i�����B���ƂɁw�A�����u�}���E���[���b�p�x�́A�t���X�R�Ƃ����Z�@��p���A�M���V���_�b�����`�[�t�ɂ����ӗ~�I�ȍ�i�̗�ł��낤�B
�@���N�̑�W��s�V����a�G��W�t�ɂ́w���{���m���x[���{��]�A�w����̌��h�ɕ�����O����x[�ڽ�]�A�w�a���҃T�����x[�ڽ�] �A�w�L���X�g�~�a�x[�ڽ�]�A�w��l�̓V�g�x[�ڽ�]���o�i�B����ɐ������ꂽ�B
�@�Ȍ�A1931(���a�U)�N�Ɂs�V����a�G��t�����U����܂ŁA����Ƃ��ĐϋɓI�Ɋ�������B
�@��1928(���a�R)�N�P��15���A�H���ƒ��J�열�O�͒m�l�̏Љ�Œm�荇�����e�r�o�ƌ����A���т��\�����B
�@�H�̔��Z����ɂ�����1919(�吳�W)�N�ȗ��A�А��̎R�{�����Y�Ƃ̈ꕔ���ɉ��������݂����A�~�T���������Ă����B���̏W���ɘH���o�Ȃ��Ă������A�܂��A�A����̘H�̋��Ђ͂ǂ̋���ɑ����Ă������͍��̂Ƃ��떢�����ł���B
�@�����i���悩�番���Ɨ����ĉ��l���悪�V�݂��ꂽ�ہA�R�{�Ƃ̉����������ǂ���ɁA�s�А�����t�����݂����(��q)���A����͘H�������𗣂ꂽ����ł���B
�@
���{���̃t���X�R�lj��@�@�H�̋A������1927�N�́A���c�}(���c����)�̊J�ʂ����N�ł���B���c�}�d�S�n�ݎ�=�����ߏ�(1863-1945)���A�Ƃ��Ƀ����h�̐���ɕ����鐹�������Ă邱�Ƃ���]���ꂽ�����̐Í]��(1893-1971)�̈ӂ��Ėk�����S���]�����1196�Ɏ��I���������݂����B���̕lj搧���H���˗����ꂽ�̂ł���B
�@���1928(���a�R)�N�V���ɏv�H���A���J��H�ɂ����{�ŏ��̃t���X�R�lj悪�ǖʂ��������B���̌�A�H�́w�쑽������N�G���x�Ƃ������ڂ̊G���������삵(���̕ӁA�����ɂ���a�G(��܂Ƃ�)��Ƃ�)�A1929�N�̑�X��s�V����a�G��W�t�ɏo�i��A������ɔ[�߂�ꂽ���A���݂͓�����i���قɕۊǂ���Ă���B
�@�Í]���̎��I�����́A1931�N������i����Ɍ��[����A��������s�J�g���b�N�쑽������t�ƂȂ����B���c�}�����ł͍ł������J�g���b�N����ł���B
�@���{���̃t���X�R�lj�́A1978�N�A������̍ۂɘH�̒�q�̋{���~�g���ɂ��X�g���b�|����ĕۑ�����Ă������A�쑽���w�O�̌��ݒn�Ɉړ]��͐��ʕǂ̐���q���������������ɕ�������A���E�ǖʕ����͐ɂ�������������Ă��Ȃ��B
�@1928(���a�R)�N�A ���㕗���G���w�y���x(����J��O���y���ɂ�����R�y���̉��t��`��������)�𐧍삵�A�{���ȑ��Ƃ����L�^������B���̌��㕗���G���́A�����f�u�𒆐S�Ƃ���s�V����a�G��t�̒��j�I�ȓ��{���12���ɂ��A��ŁA���{�����O�̊ۏ����قɎ��߂��Ă���B
�@������11���R���A�����߂ɒ���=�S�����a�����A�H�͕��e�ƂȂ����B
�@������1929(���a�S)�N�A�P��30������12��20���܂ł̖����A�����V���ɘA�ڂ̑��(�����炬)���Y(1897-1973)�̎��㏬���w���炷�g�x�̑}�G��S�������B�̍��ؘa�j���ɂ��A�u���̉�͖����A�H����̂��ꂳ�V���Ђ܂œ͂���̂��Ǝ��̑c�ꂪ�b���Ă����v�Ƃ̂��Ƃł���(�w�����C�ݕS�N�̗��j�x)�B
�@�A�ڏI����A�����Ђ���O��тɕ����Ċ��s���ꂽ�P�s�{�w���炷�g�x�̑���A���G�����R�H���S�������B
�@���݂����͉��l�́s��Ŏ��Y�L�O�فt�Ō��邱�Ƃ��ł���B
�@�S���P���ɂ͏��c���}�s�S���]�m�������J�ʂ��A�����C�݉w���J�݂��ꂽ�B��k�Ђ̕������ȗ��A�����암�͂��Ă̕ʑ��n�����Z�Z��n�ɕϖe�����������A���c�}�J�ʂ͂��̌X���ɔ��Ԃ��|���錋�ʂƂȂ����B
�@�H�̑ؕ����ɁA�����f�u�̒�����̌Z=�����×Y���C�R��ޖ����A�����ł̊w�������ɓ����Ă����B�f�u�́A���c�}���J�ʌ�͎��܍����̌Z=�×Y�@��K��A���̓s�x���J��H�@�ɂ�����o�����悤�ł���B
�@���̔N11���A�H�͏��߂Ă̌W���s�����S�����t�i����w�k���A���݂́s���H��c���t�t�߂ɂ������j�ŊJ�����B�o�i��́w���ɔg��x[���{��]�A�w�ᒆ�����x[���{��]�A�w���|�~�x[���{��]�ȂǁA���{�悪���S�ł���B
�@
���E����@�@1930(���a�T)�N�̑��t�A30��̒��J��H�ͤ�s���n(���[�})�J�Ó��{���p�W�����t�̓��{����\�ł���60��̉��R���(1868-1958)�A50��̕���(�Ђ�ӂ�)�S��(�ЂႭ����)(1877-1933)�A40��̏����f�u(1881-1938)�e���̐����Ƃ��ăC�^���A�ɓn�q�����B���̑��ɂ���q����(���������傤����)(1882-1958)�A������M(�͂�݂��債�イ)(1894-1935)���n�ɂ��Ă���B
�@�s���n�J�Ó��{���p�W�����t�ͤ1930�N�̂S��26������U���P���܂ŁsPalazzo delle Esposizioni(���[�}�s���W����)�t�����Ƃ��čs�Ȃ�ꂽ���̂ŁA�@�W���W���킸�A������d�Ŋ�������̓��{��Ƃ������V���ߍ�\������K�͂ȓW����ł������B�v���f���[�X�͑�q�����̑���=��q�쎵�Y�i1882-1963)�A�^�c�ɂ͉��R��ς��������Ă���B���̎��b�\���[�j(1883-1945)�𑍍قɂ������čs��ꂽ���킭���̂��̡���̎��̑�\�́A�qCavaliere Corona de Itaria(�C�^���A���a�����J�M��)�r���C�^���A���{����Ă���B
�@�H�͂��̋@��Ƀ��@�`�J����K��A��260�㋳�c=�s�E�X11��(Pope Pius XI)(�݈ʁF1922-1939)�ɔq�y�B���̐܁w�؎x�O�֑ɗ��x[���{��]�����悵�Ă���B
�@�V�X�e�B�i���p�قɁwIntroduccion del Cristianismo en Japon�x[���{��]��1925�N�Ɋ���Ă��邩��A���̍ۂ��q�y�̉\�������邪�A������ɂ���H���q�y�����ŏ��̋��c�ł���B
�@��q�쎵�Y�́A�P�����]��ɂ킽�邱�̓W����̈ԘJ�̂��߂ɁA�A�r�͉��Ă��o�R���鐢�E������s����s�Ƀv���[���g���A�N���ɂ͋���������M�������[�ɂās���E����X�P�b�`�W�t���J�Â��ꂽ�B
�@�A�������H�́A�l���̗m���=���X�؏����Y(1897-1973)��Ɓs�J�g���b�N���p����t�����������B���X�N�̑�P��s�J�g���b�N���p����W�t���A�n�ɑO�N�̑�10��s�J�g���b�N���p����W�t�܂łقژA������(��V���L�^����������Ȃ�)�o�i���A���S�I�Ȗ������ʂ������B
�@��1931(���a�U)�N�U���ɁA����c��w���z�w�ȂŘH���u���������ہA�W�{���Ńt���X�R�̎��������Č������B���̌�A���̊G�̏ォ��h�����h���A�����ԏ��݂��s���̂܂܂ł������B
�@���ꂪ1996�N�ɂȂ��Ĕ�������A�U�w�̓h���J�ɔ������āA�H�̒�q�A���c���q�A�F�R�q���q�����̎�ŏC�����Ȃ��ꂽ�B1998�N�A���̌���������邱�ƂɂȂ�A�����̊O�ǂ��̂��̂�ؒf���A���̔N�ɊJ�݂��ꂽ�s���(������)����(�₢��)�L�O�������t�Ɏ��[�A�W��(http://www.waseda.jp/aizu/col3e.html)����邱�ƂɂȂ����B���̌o�܂́A���ق́w�����I�v�x��P���ɗL�c �I�������Ă���B
�@�s�V����a�G��t�͂��̔N�ɉ��U���A�H�́w�ΔȂ̂܂ǂЁx[���{��]���12��s��W�t�ɏo�i�����B�Ȍ�A�s��W�t�ɂ́s�V���W�t�ɑւ��1934(���a�X)�N�܂Ŗ��N�o�i����B
�@��������̌㔼�ɂȂ��āA�H�͎���A�g���G�ȂǂŎ����ƐN�����̂��߂̉�m���J�����B�N�ɂ͐p�f�b�T������ʂƂ������m��̋Z�@���������炵���B�����q�ɂ͌��݂������Ɍ䌒�݂̕�������������B
�@ 1932(���a)�V�N�A�H�͓����I�����_�̃C���h�V�i(����)���������݂̃C���h�l�V�A�̃W�������A�o�����Ȃǂ��K���A���̈�ۂ��w�M���̖�x[���{��]�Ƃ��Đ���A ��13��s��W�t�ɏo�i����B
�@���̊O�V���Ԓ��A�W���P���ɓ�=�S���q���a�������B
��a�{���@�@�J�g���b�N�̌h�i�ȐM�҂ŋ���ҁA�ɓ��Í](�H�����{�ŏ��̃t���X�R�lj��`�����쑽����������Ă�)�ɂ���� 1929(���a�S)�N���c�}�]�m�����J�ʂɍ��킹�č����S��a��(����a�s��ъ�)�ɐݗ����ꂽ�s��a�{�����{�Z�t�́A������ʓI�ł������ǍȌ���^�̏��q����̊T�O��傫�������A�y�ɐe���ݎ��R�ɐG��钆�Ő_�̐ۗ������邱�Ƃ����痝�O�Ɍf�����v�V�I�Ȋw�Z�Ƃ��Ďn�܂�A�]������(����)�A�v�ۓc�����Y(����)�A�l�ƕ��q(���y�j�Ƃ��������̓��ɂ����钘���ȋ����������ꂽ�B���J��H�����̈�l�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@��1930�N�ɂ́s��a�{���������{�Z�t�Ɖ����B1932�N�ɂ́s��a�{�����{�Z�t�A1935�N�ɂ́s��a�{���c�t���t���J�݁B�ɓ��Í]�̋���ڕW�ł���u�J�g���b�N���_�ɂ��L���Ȑl�Ԍ`���v�́A�������炩�璆������(���͒Z����J��)�ɂ킽���т������琧�x�ɂ���Č`����邱�ƂƂȂ����B�H�͓�������̂��鍔������ł��߂��J�g���b�N�n�~�b�V�����X�N�[���ł��������Z�̔��p���t�Ƃ��āA1929�N����A���炭�ڔ��ɓ]������1937�N�܂ŋ��d�ɗ������B
�@�܂��H�́A�w����ɂȂ�������=�S����������w�Z�ɓ��w�������B
�@�Ȃ��A�s��a�{���������{�Z�t�͐��̐V�w���Łs��a�w�����q�����w�Z�t�ɂȂ�A�����1979�N�s���Z�V���A���q�����w�Z�t�Ɖ��߂č����Ɏ����Ă���B�����ɂ́s��a�{���������{�Z�t�ł̘H�̋����q�Ƃ����������l��������B
�@
����@�lj��@�@1933(���a�W)�N�A���̃t�����X�Ɍ������u���Ίہv�̑D��Œm�Ȃ���������Ƃ̓���=����`�e��݂��A�����ڔ��ɂ���������������̌˓c(�I�B����Ƃ̈���)�@�ՂփC�M���X�̃e���[�_�[�l����͂������@(�v�F�n��
�m(����))�����Ă邱�ƂɂȂ����Ƃ��A�H�͊K�i���A�H���̏㕔�Ɂw��}�x�A�w�Õ���x�Ƃ����t���X�R���`���A�C���e���A���f�U�C�������B���ꂪ���������œ����݂Ƃ̌𗬂��[�܂邱�ƂɂȂ�B���̖ڔ��̓���`�e�@�́A�������P�̐������Ƃ�A���q�{�K�@�̉��Z�ɂɗp����ꂽ��A���͓��{�Љ�}���}�̕���ɂȂ�����Ƃ����b�肪���邪�A1968(���a43)�N�ɉ�̂���A���쌧��ӎR�����Ɉڒz���ꂽ�B��̂̎��A�H�̃t���X�R��͘H�̒�q=�{���~�g���̎�Œ��J�ɃX�g���b�|���ꂽ���A�����Ɉڒz��ɕ�������Ă��Ȃ��B
�@�ڒz���ꂽ�����́A�����z�e���Ƃ��Ċ��p���ꂽ�B���݂́s�����x�����q���b�e�t�Ɩ���ς��A���X�g�����ƃe�B�[���E���W�Ƃ��āA�ċx�݁A�S�[���f���E�C�[�N�̂݉c�Ƃ��Ă���B�R�c���ꌴ���TBS�h���}�w�����ւ�������Ⴂ�x�̕���ƂȂ�A�l�C���o���B�߂��ɂ́s����s�����x��O�̌������t������B
�@������1935(���a10)�N�A����@�̕~�n���Ɍ��Ă�ꂽ�s���c�@�l�����t����쐶���������t�̌��z�����ɏ]�����A�V����`�����B����͌�������B
�@���̔N�̏t����Ăɂ����āA��p������A���s���̂S��16���ɎO��=���q���a�������B���̗��s�ł͗���̑�k�����قŌW���J�����肵�Ă���B
�@1935(���a10)�N��W�̉��g�ʼn�d���傫���h��A�����f�u�͒��N�߂���Z�������p�{�Z�������A���N�X���ɖ剺�����킹�s����@�t�����������B
�@������ЁA�g�c�H���A�����L�P�A���R�����A���ؕ۔V���A��c�����A�R���H�t�A������A�g�����v��Ƌ��ɒ��J��H�����������o�[�̈���ƂȂ����B
�@����̑n����ڎw���A��a�G�𒆐S�Ƃ��Ȃ���W����͗m��A�����ɂ���˂��J�������A1937(���a12)�N����W���J�Â����݂̂ŁA���N�̉f�u�̎����ɂ��W��������x�~�A�����c�̂Ƃ��đ������A1943(���a18)�N���U�����B
�@1936(���a11)�N�A�s�t�H���e�[�k�u���E�������t�ɂ�����t���X�R��A���U�C�N��̎t=Carlo(�J����) ZANON(�U�m��)���������A�H��K�˂č����ɂ��؍݂����B�����ɂ͘a�������Ȃ����߁A1933�N�ɓ����s�̖���=���q�v�Ȃ����Ă��m���́s�����z�e���t�ɏh�������Ƃ����B
�@
���������w�@�@�@���؈ɎO�Y���A���������Y�ƂƂ���1919(�吳�W)�N�A�����̓����ԍ��R�쒬�ɊJ�݂����s���ؕw�l�q�����ٖD�������t�́A1935(���a10)�N�Q���T�����c�@�l�s���؛{���t�ɑg�D�ύX���s���A�w�Z�Ƃ��Ă̊�b���ł߂��A1936(���a11)�N10���Z�����s���������{�@�t�ɉ��߁A����̕ω�����肵��������e�̊g�[���s�����B���̒i�K�œ���`�e�̏Љ�(���{�����Y�̏Љ�Ƃ�����������B���炭�o���ł��낤)�ŁsEcole du Louvre�t�Ő��m�����j���C�߂����=���J��H�̑��݂�m�������́A1937(���a12)�N�Q���A�����������̘H��ɔh�����A�����ɓ����点���B���������Y�͐��l�`����݂₰�ɘH���K��A���������B�H�͈�U�f�邪�M�S�Ȑ����ɐ܂�A�S�����狳�d�ɗ����Ƃ����������B�Ȍ�A�I�����������w�@�Ƃ̊W�͑������ƂƂȂ�B
�@�����ڔ��̓����ݓ@���ӂɑ������ꂽ�����n��D��I�ɍw���ł����H�́A�悸�A�g���G�����āA�����ŕꉮ�����z����1937(���a12)�N�Ɉ�Ƃ͓]������B
�@�������Ē��J��H��10�N�ɂ킽�鍔������͏I����������̂ł���B
�@
�k�Â��l(���̎҂͌h�̗�)
�i�킽�Ȃׁ@��傤�j
|
||||
